前職倒産から考える適者生存
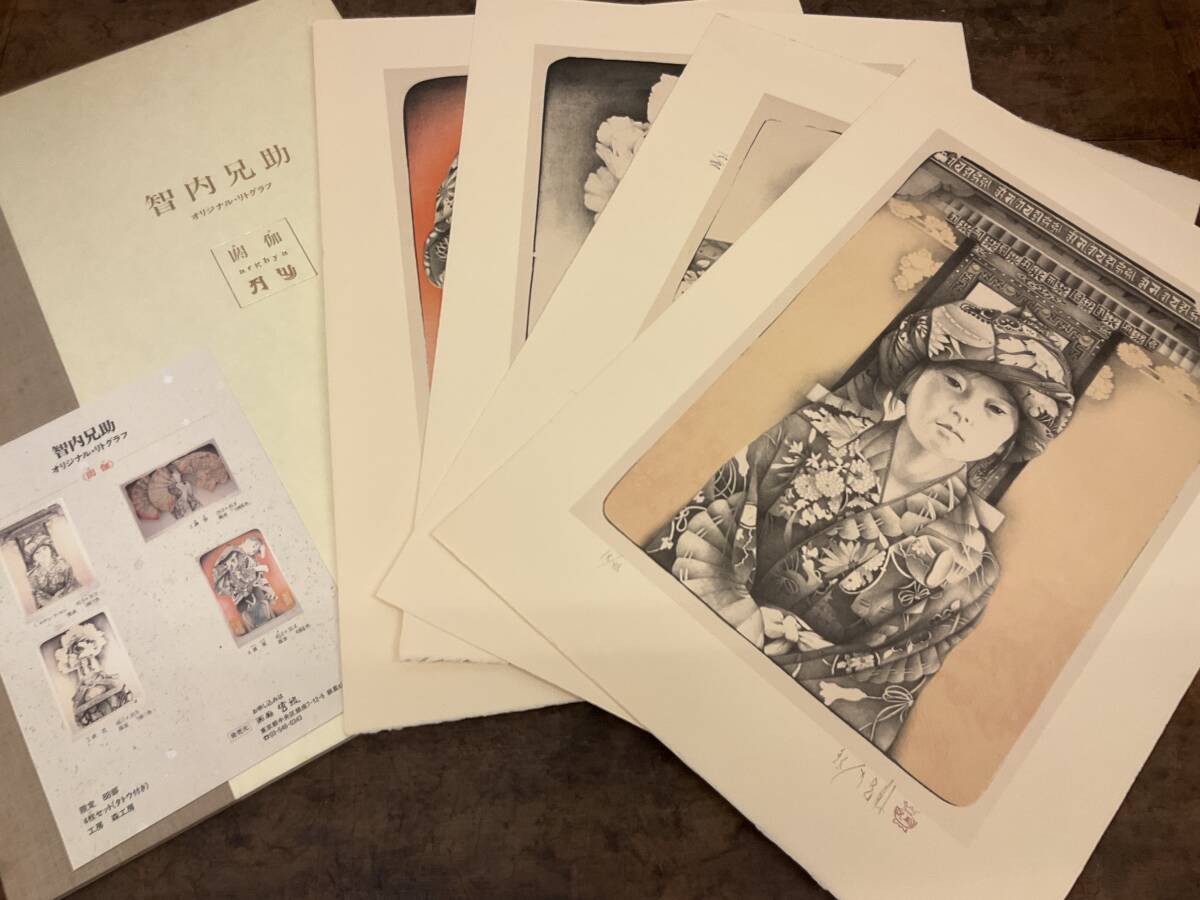
私はこの業界に入る前(20代の頃)は異業種で働いていました
その会社は車バイク業界の広告代理店・出版社で、まるで関係のない業界で営業をしていました
バイクショップに電話営業をしたり、飛び込み営業もしていましたし今思えば若かったこともあり休みなく働いていたと思います
後はバイクパーツメーカーからバイクメーカーまでクライアントも幅広く、ストレスもありましたが忙しく飛び回っていました
会社規模も入社した時は15人くらいでしたし、創業間もないいわゆるベンチャー企業だったので営業しながら他部署(編集部)の手伝いもしていて、会社に泊まり込みも月に数日はありましたし、休みも月に2-3日とれるかどうか、休日手当も残業代もなく、さらに給料は薄給でした
まぁいわゆるブラック企業と言われればそうだったと思います
そのため新人が入ってもすぐに辞める人も多く(まぁ当然ですが)常に会社全体が忙しかったです
在職している時もそういう状況だった事もあり、業績も良かったり悪かったりしていました
ボーナスが出る事もあれば給料がカットされる事もあって、私は当時は独身だったのでまだ良かったのですが家庭がある先輩は大変だったと思います
でもそんな中で新規でクライアントを獲得したり、長くいい関係を築けたり、クライアントが儲かって大きく成長したりするとやりがいを感じて給料低くても、なんとか耐えられました
そうやって関係を築いたクライアントとは今でも付き合いのある方はいますし、起業してからも大分助けてくれた恩人もいます
それでも自分が本当にやりたい事がその業界ではなく、年齢的にも20代のうちに動きたかった事もあって、結構悩みましたが入社してから7年半で退社しました
退社してからはずっと今の業界にいますので、仕事として携わることはなくなりましたが同僚との付き合いは続いていたので、会社の状況などはなんとなく聞いていました
やはりいい時期もあれば悪い時期もあるという感じで推移していましたが、出版(雑誌)業界自体が衰退していったので年々苦しくなっていったみたいです
私が新卒で入社した頃が雑誌の売上はピークで1兆5000億円以上あったのが、今では4000億円程にまで下がっているようです
またバイク業界も私が入社した頃は200万台以上売れていたのが、最近は50-60万台を推移しています
また雑誌を絡めたイベントも積極的に開催していて、それも一つの大きな柱だったみたいなのですが、これらがコロナ禍によって全てがストップしてしまってさらに苦境に陥ったと聞きました
その後色々と手は打ったと思いますが、規模も50人程になっていましたし、一度悪い方に進んでしまうとなかなか回復するのが難しかったのでしょう
結果、数年前に倒産していました
その後社員の多くは買収した別の会社に移籍して(雑誌は継続)働いていますし、社長をはじめ移籍していない人達も新しい場所で頑張っているようです
そして元同僚とあって話をしていると「会社というより業界が大きな変化があったのに、昔のやり方に固執したのが不味かったのかなぁ」という事を聞きました
もちろんこれは結果論ですし、ちょっとした事で状況は変わったのかもしれませんが、私も小規模ながら会社を経営していますし、社員もいますので知識として吸収するべきところはしようと思っています
昔のやり方に固執したというのは、雑誌作りに心血を注いで良いものを作れば必ず売れるという考えで突き進んでしまったという事だと思います
やはり雑誌自体が売れなくなってきた時代の中で、売れていた時代と同じやり方を踏襲していてはなかなか難しかったかもしれませんし、広告にしても紙媒体だけでなくもっと早くネットに移行していけば違ってたかもしれません
もちろん私ごときが言えることではありませんが、やはり時代や業界の変化には敏感に対応していかなければなりません
骨董リサイクル業界の市場自体は拡大していますが、大手の伸長は凄まじいですし個人間取引(メルカリなど)も伸び続けています
そんな中でこれからも同じやり方を続けていけば、今はいいかもしれませんがあっと言う間に取り残されて最悪倒産という事も無い事ではありません
もちろんどの業界もそうですが大手が中小を駆逐する弱肉強食の世界でもありますが、一方規模は小さくても環境に上手く適応して生き残る適者生存の世界も私はあると思っています
正直これから規模をどんどん拡大していくつもりはありません(必要な投資はもちろんしていきます)
ですので規模ではこれからどんどん大きくなる大手にはますます歯が立たなくなりますが(買取価格で勝てないという事ではありません、念の為)それでもお客様の要望を的確に吸い上げて、そこにしっかりとアプローチして適正な買取価格を提示できれば私はまだまだ生き残ってはいけると思っています
その為にも日々回っているお客様の話をしっかり聞いて、今の時代に必要な事を常にアップデートしていかなければなりません









